「わかってくれるはず」は、思い込みかもしれない
誰かに優しくしたとき、あなたはどんな気持ちになりますか?
「きっと喜んでくれる」「感謝してくれるはず」そんな期待が心のどこかにあるかもしれません。
でも、その通りにならなかったとき、がっかりした経験はありませんか?
この記事では、人間関係や日常生活に潜む「期待しすぎ」のクセに気づき、少しラクになるための考え方をご紹介します。
どうして私たちは期待してしまうのか
期待は自然な感情です。家族や恋人、同僚に対して「こうしてくれるだろう」と思うこと自体が悪いわけではありません。
問題になるのは、「自分の期待通りに動いてくれなかったときに、相手を責めたり、自分を責めてしまうこと」です。
心理学ではこれを「認知のゆがみ」と呼ぶこともあります。
たとえば「私はこんなにしてあげたんだから、あなたも同じだけ返してくれるはず」という考えは、無意識に「見返り」を前提にしている状態です。
期待しすぎない=冷たくなる、ではない
「期待しないようにしよう」と思うと、なんだか冷たい人になる気がしてしまうかもしれません。
でも、それは誤解です。
本当に大切なのは、「相手に自分の期待を押しつけないこと」。
期待はしてもいいけれど、それが満たされなかったときに怒りや悲しみに引きずられないよう、心の余白をもっておくことがポイントです。
これは「マインドフルネス的な姿勢」にも通じます。
今この瞬間の感情や相手の反応を、評価せずにただ受け止める。
その実践については以下の記事もご参考ください。
👉 マインドフルネス初心者ガイド
「勝手に期待して、勝手に落ち込む」のループを抜け出す
たとえばこんな場面、思い当たりませんか?
・仕事で頑張ったのに上司に評価されない
・家族に愚痴を聞いてほしかったのに、話をそらされた
・恋人が特別な日に何もしてくれなかった
これらはすべて「相手がこうしてくれるだろう」という自分の期待が前提にあるからこそ、強く傷ついてしまうのです。
このループから抜け出すには、「期待している自分」にまず気づくこと。
そして「相手には相手の事情や感情がある」と理解し、自分の気持ちだけを丁寧に見てあげることが大切です。
自分に優しくするためにできること
- 「期待してたんだな」と気づいたら、それを責めずに認める
- 「こうしてくれたらうれしいな」と言葉にして伝える練習をする
- 自分の感情をノートやメモに書き出してみる
- 「期待を持たない」より「余白を持つ」と言い換えてみる
- 相手の反応に左右されず、自分の行動に納得できるよう意識する
自分に優しくすることは、他人への優しさにもつながっていきます。
まとめ:期待しすぎないという優しさ
- 期待は自然な感情。悪いものではない
- ただし過剰な期待は、自分も他人も苦しめる
- 「見返り」を前提にしない関係性を目指す
- マインドフルネス的な受け止め方がヒントになる
- まずは「自分の気持ち」をやさしく見てあげよう
あなたは、あなたのままで大丈夫
人に優しくするあなたは、きっと素敵な人です。
ただ、ちょっとだけ「期待」と距離を置いてみましょう。
もっと軽やかに、もっと自分らしく過ごせる日がきっと増えていきます。
今日も「たのもしいクマさん」に来てくれて、ありがとうございます。
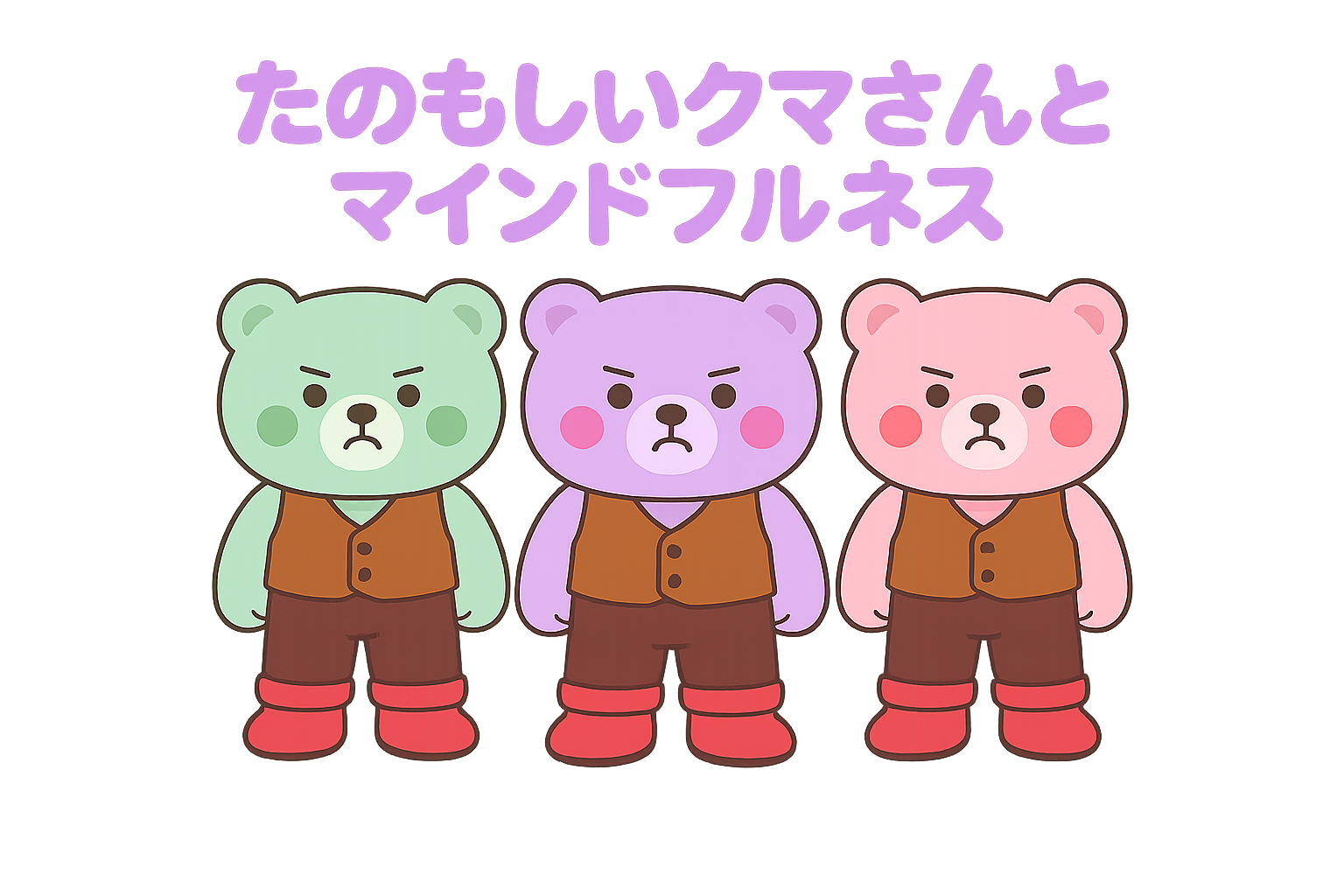



コメント